受験対策ブログ
小学生にしてほしい!国語の勉強 短文を書く・メモを取る

進歩をとげるAIの学習法、人間の勉強法とどんなち違いがあるのかを調べました。
そうすると、これからのAI時代を生きる今の小学生に求められる国語の力とは何かがよくわかってきました。
AIとは異なる人間だからこその国語の勉強法をご紹介しつつ、国語の究極の勉強法はこれだ!という一つの答えを示します。
短い作文を書いて国語力をつける勉強法
1. 作る短文は身近なできごとがよい
2. 体感型の記憶として言葉を覚える
お子さんは「AI読み」をしていませんか?
1. 東大合格を目指したAIの話
2. AIの国語の解き方はむちゃくちゃだった!
3. なぜAIは非常識な選択肢を選んでしまうのか!?
4. AI vs. 教科書が読めない子どもたち
5. 子どもたちは教科書がなぜ読めないのか?
6. 小学生が身に着けるべき 21世紀型スキル!
AIを超える!究極の国語勉強法
1. 究極の国語勉強法とは何か?
2. できる子はみんなメモを取る!
3. 国語はプログラミングできるのか?
短い作文を書いて国語力をつける勉強法

人間の記憶法の特徴ですが、コンピューターにインプットさせるのと同じような単純暗記ではありません。
たとえば、新しい漢字や語彙を覚える場合、過去の記憶と新しく覚える漢字・語彙とを関連付けして覚えているのです。
この記憶法を生かした国語の勉強法は何だろうかと考えて、今回ご紹介するのが「短文作成」勉強法です。
この後からは具体的に「口火を切る」という言葉を使って、短文作成勉強法を詳しく説明します。
1. 作る短文は身近なできごとがよい
日頃、わたしは授業で読んだ文章に「覚えてもらいたい言葉」が出てきたら、その言葉を使った短文作成の宿題を出しています。
宿題で作る短文は、自分の身近なできごとがよいです。
なぜなら、新しい言葉を覚えるためには、自分のことと関連付けた方が記憶が定着しやすくなるからです。
2. 体感型の記憶として言葉を覚える
新しく覚えた言葉は、記憶の巨大なネットワークに収納されます。それは巨大な倉庫の中に小さな品物を一つ保管するのと似ています。
保管の際、保管場所までの通り道で目じるしになるものをたくさん覚えたり、作ったりしておくと、次回行くときにスムーズですよね。
保管箱の番号を覚えるのもいいですが、それは単純記憶なので、人は忘れてしまいがちです。

でも、途中にあるドアノブのひんやりした手ざわりや、通路に飾ってあった絵など、感覚的、体感的な記憶と関連付けすれば、たどり着きやすい。
つまり自分の記憶として定着させることができるのです。
短文作成はこれと同じです。
経験した過去の記憶を使って、言葉を自分のものにする方法です。
「口火を切る」という慣用句を宿題に出したとします。
② 次に「口火を切る」の意味を辞書で引きます
③ 辞書で引いた意味をノートに書き写します
「口火を切る」・・・・・・「ものごとを他より先におこなって、きっかけをつくる」
ここまでならよくある辞書引き、意味調べの宿題です。
これでは機械的に行うだけで終わってしまいます。
「機械的」な作業はコンピューターにもできることです。
「コンピューターにできないやり方をする」
これが今回のテーマです。
ここからがポイントです。

④ 調べた言葉を使って、短い文章を書いてみましょう
言葉はその用法を身につけて、ようやく自分の語彙になったと言えます。
言葉を覚えたタイミングで、用法も覚えるようにしましょう。
短文を書くときですが、すぐに始めるのではなく、辞書に載っている例文を参考にするとよいです。
⑤ 例文を読む
例文が「先生の説明が終わると、佐藤さんが質問の口火を切った」と載っていました。
例文を読むと「口火を切る」を使う場面のイメージがわいてきますね。
単に言葉の意味だけを知ったときよりも、より理解できます。
⑥ 例文を自分の話題に置き換えて書く
例文の場面と同じようなことが自分のまわりのできごとにないか。
自分の身のまわりに置き換えて考えてみてください。
思い浮かんだできごとを書き出しましょう。
授業中にあったできごとをあなたは思い浮かべたとしましょう。
そして、書いてみたのが次の短文でした。
「わたしたちの班の発表が終わると、田中くんが口火を切って発表内容への反対意見を述べた」
これで宿題としての当初の目的は達成されました。
しかし、欲を言えば、もっと詳しく文を書き足すとさらに良くなります。
そうするとなぜ良いのか。
表現力を身につけるトレーニングにもつながるからです。
文を書き足すときのテクニックは「接続語」や「感情を表す言葉」を使うことです。
⑦ フィクションをまじえて書いてもOK
一字一句かならず実際に起こった事実だけを書く必要はありません。
こんなことなら、まわりでありそうだなという脚色、フィクションをまじえてもかまいません。
短文作成の目的は事実を書き写すことではなく、新しい言葉を使って身近な題材を文章にすることにあります。
気楽に思いついたことを書き出してほしいのです。
短文作成の宿題を出すと、自分の身のまわりで起こったようなフィクションを、ノート1ページにびっしりと書いてくる生徒がいました。
最初、国語が苦手だと口ぐせのように言う生徒でした。
ですから、短文作成の宿題を書いてきたとき、その熱意を褒めました。文章は「てにをは」がおかしいところがありました。
でもまずはそれでいいのです。
彼はこの宿題でフィクションを書くことの楽しさを知ったようでした。
短文作成を通して文章全般、「書くこと」に慣れていきました。
当初やり方がわからないからと言って無回答で出していた記述問題に手をつけるようになりました。
作文も率先して取り組むようになっていきました。
⑧ どうしても短文のアイデアが思いつかない
身近なできごとで気楽に書き始めることをおすすめします。
しかし、どうしてもアイデアが思いつかない場合は、ネットで言葉を検索して、題材を見つけて書き写してもかまいません。
そのとき、「ニュース検索」をすると、記憶と関連付けしやすい題材がたくさん出てきますよ。
たとえば、「口火を切る」でニュース検索をかけると
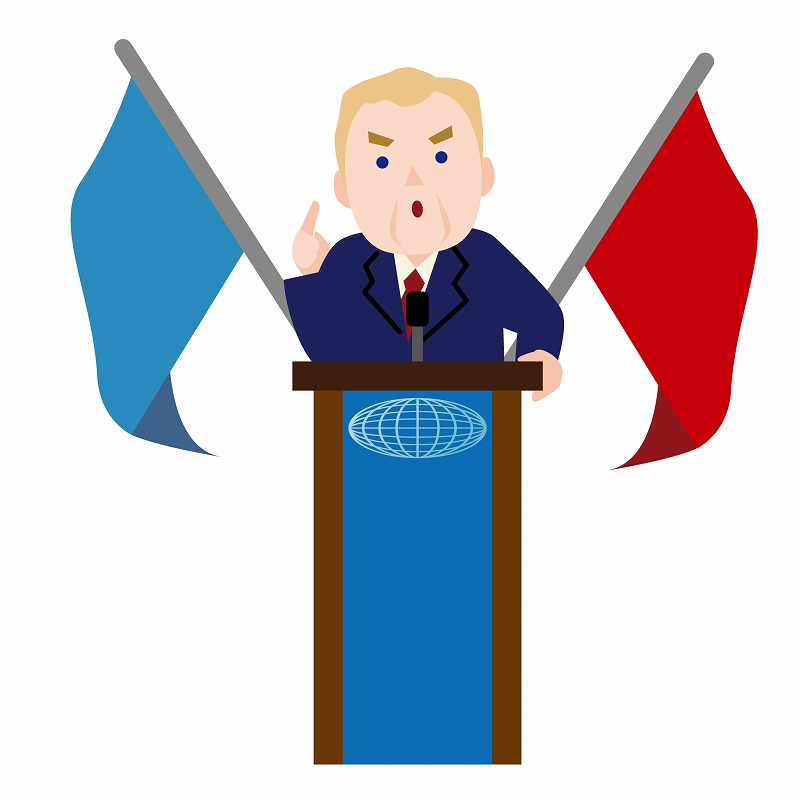

「大谷が四回に口火を切る安打を放った」
などが表示されました。
ニュースはイメージがわきやすく、記憶に残りやすいできごとの宝庫です。
お子さんは「AI読み」をしていませんか?
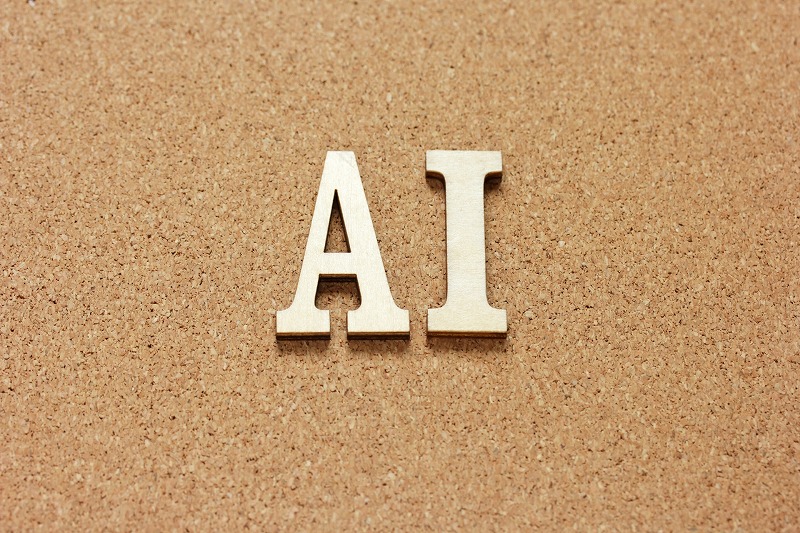
AIの学習法と人間の勉強法の違いを調べていると、入試問題をAIが解くプロジェクトを見つけました。
そのプロジェクトは東大入試合格を目指して開発を進めていた人工知能(AI)の「東ロボくん」のことです。
この東大ロボが国語の勉強法
小学生が国語を学ぶうえで、良い反面教師になるものでした。
そのため、続いてこのAIロボットについて書いていきます。
1.東大合格を目指したAIの話
人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」: 第三次AIブームの到達点と限界
この東大ロボは模試の偏差値が数学で76を越え、全国の大学の8割にあたる472の大学で「合格率80%以上」を示すA判定を獲得するまでになりました。
ところが、東大ロボは壁にぶち当たりました。
苦手科目の国語を克服できる見通しが立たなかったのです。
このため、2016年秋をもって、このプロジェクトは終了し、東大合格を目指すことは断念されました。
2. AIの国語の解き方はむちゃくちゃだった!
東大ロボは設問文と選択肢の「文字の重複度合」や「選択肢の文の長さの妥当性」など、データ処理を行って、正解・不正解を判断しています。
国語の中でも評論文のような論理的な整合性を問う問題では、50%以上の正答率を獲得するそうです。
ここまで到達していた東大ロボですが、壁が存在するのには明確な理由がありました。
東大ロボは、実は文章をまったく読まないで問題を解いているのでした。
現在のAIでは「意味」による判断ができないのです。
つまり、言い手がどんなとらえ方でその表現を選んだかが判断できません。
あくまで、データに頼った統計処理で判断しているだけです。
これでは評論文の選択肢問題は文の重複度でできるかもしれませんが、小説は解けません。
入試の小説は文中のセリフや行動から、その背後に隠れた登場人物の心理を推測して答える問題です。
たとえば「顔を赤くする」のは、場面によって使われ方が変わります。恥ずかしがっているのかもしれませんし、怒っているのかもしれません。
どちらの意味で使われているのか文章の前後関係で判断するわけですが、文書を読まない東大ロボにはそれができません。
3. なぜAIは非常識な選択肢を選んでしまうのか?

次のような問題も東大ロボにはできませんでした。
Bさん「待って。( )」
Aさん「ありがとう。いつもなるんだ」
問.( )に入るのは①②どちらか?
①長いこと歩いたよ
②靴ひもがほどけているよ
正解は②
しかし、東大ロボは①を選んでしまったそうです。
東大ロボはどう考えたかというと
②「歩く時間」が書かれた文が前後にある場合、解答は「時間に関する文」が入る確率が高いという統計判断を行った
その結果、東大ロボは間違った選択肢を選んだのでした。
東大ロボには「人間がお礼を言う状況」という「常識」がないのです。
「Aさんが、Bさんの言ったことに対して感謝している」という状況を理解していません。
だから、こういった状況の場合、当然こんな会話がされるだろうという常識的な判断ができないのです。

もう一つ、AIの「常識」にまつわる例をあげると
母と娘が父のためにバースデーケーキを作っている物語の問題を解くために、仮に「バースデーケーキ」とは、どんなものかという「常識」をAIに膨大な数インプットさせたとしましょう。
しかし、バースデーケーキがローストチキンやちらしずしに変わっただけで、AIは他のごちそうについての「常識」がないので、もう解けないのです。
このように人間だったら、当然子どももわかるレベルの「常識」がないため的確な判断ができず、問題が解けないのです。
仮に1つの設問を正解するために、膨大な数の関連する文例を読み込ませる必要があるのですが、それがなんと500億個も記憶させる必要があるそうです。
そういった文を自動的に収集できる仕組みが現在はありません。
そのため、行おうとすると人に頼らざるを得ません。
人がデータを作成した場合の人件費を計算すると、ざっと500兆円の費用がかかってしまうそうです。
現実的ではないため、AIでの東大合格プロジェクトは断念されたのでした。
4.AI vs. 教科書が読めない子どもたち
AIの敗北、人間の勝利?
いいえ、東大ロボの話はここからが耳の痛いところです。
AIは文章の意味をわかって読んではいない。
それなのに全国の8割の大学で、模試の合格率判定で80%を出す。
ということは、AIより受験生が読めていないことになる。
そこで、東大ロボの開発者・新井紀子教授は、中高生の読解力を調査したところ、中高生よりAIの方が文章を読めている事実に直面したそうです。
「AIの性能を上げている場合ではない。中高生の読解力を高めなければならない」と考え、新井教授は現在、中高生の読解力向上を目指して調査・研究をしているのです。
5.子どもたちは教科書がなぜ読めないのか?
新井教授らによる中高生の読解力調査はどういうものかというと、全国2万5000人の中高校生を対象として、教科書をベースに1,000問以上の問題を作成し、日本語の文を読んで意味が理解できるかを測るものでした。
その出題例をあげます。
例えば、次の問題ですが、対象者の約3~4割が正答を選べなかったそうです。

仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアにおもに広がっている。
この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適切なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。
オセアニアに広がっているのは( )である
①ヒンドゥー教
②キリスト教
③イスラム教
④仏教
正解、②キリスト教
全国の中学生の正答率62%、高校生正答率72%
文章をしっかり読めば、答えは「キリスト教」とわかります。
問題文の中に解答が書いてあるにもかかわらず、文章を正しく読み取れないで誤答する生徒がかなりの割合でいるわけです。
同じように設問の中に正解がある他の問題でも、一定の割合で間違える生徒が存在していたそうです。
5. 子どもたちは教科書がなぜ読めないのか?
新井教授はこの結果に対してショックを受けたそうです。
「計算の正確さと暗記の正しさで人間がAIに負けることは何も問題はなく、人間はAIを使って生産性を上げていけばいい。
しかし、(AIが苦手な読解力を伸ばさずに)AIが得意とする分野で人間が対抗しても勝てないだろう」と述べています。
AIが進歩して社会に浸透していくなかで、人間は人間らしい読解力、意味を理解する能力を深めていく必要があるでしょう。
しかし、現状はまったく文章を読まず意味を理解していないAIと同じように中高生も文章読解を苦手としているのです。
AI時代到来を目前にひかえて、まず中高生が教科書を読めるレベルの読解力を身につけることが現状を見たときの課題です。
では、どうすれば国語ができるようになるのでしょう。
それもできれば、これからの時代、AIには身につけられない方法で国語の力を身につけたいものです。
6.小学生が身に着けるべき 21世紀型スキル!

ここまでAIについて調べてみてわかったことのひとつは「常識」が人間らしさと言えそうなことです。
さて、その「常識」の身につけ方となるとこれはもう昔から言われている話です。
さまざまな「経験」を通して知ることです。
または経験に代わる「読書」などを通して知ることです。
東大ロボが、実感をともなった経験がなく、文章をまったく読まないことの逆を行けばよいわけです。
今教育の世界では「21世紀型スキル」の習得が目標になっています。
21世紀型スキルとは、IT化とグローバル化が進むことを前提に定義されたものです。
たとえば
②市民性
③批判的思考
④創造力
⑤情報活用力
などのことだそうです。
一見、生活に当然必要なスキルに思えますが、AIを知っていくと、これらのスキルの習得は人としての「常識」を身につけることなのだと納得します。
では人として常識的な知恵を身に着けるための勉強とはいったいどんなものがあるでしょうか。
AIを超える!究極の国語勉強法
1. 究極の国語勉強法とは何か?
AIが苦手で、人間が得意な面を生かした勉強。
この方向性を示してみましょう。
以下のようになると思います。
②常識を体感的に「記憶」しておく勉強
③意味を理解するために「常識」を身につける勉強
④文章の「意味」を理解するような勉強
究極の勉強法はメモを取ること?
①~④に該当する勉強の1つとして、今回、短い作文を作成することを紹介しました。
この短文作成と同じ方向性の勉強法として、補足的にもう1つあげておくと「メモを取ること」があります。
何を今さら「メモを取る」なんていう基本的なことを言うのかと思われるかもしれません。
しかし、通常勉強と、とらえていない人間の生活に根ざした基本的な行動であるために、AIにはできない行動がこれなのです。
AIには今まさに現実で体験していることを、即言語化するというメモ行為は実はとても難しい作業なのです。
メモを取ることは、一見単純そうに見えて、実に複雑な処理をしていると言えます。
メモを取るとき、メモを活用するときの一連の流れを少し考えてみましょう。
① 常識を身につけるための「体験」をすること

体験していることの中で特に重要だと思った点を即言語化するのがメモすることです。
体験を言語化することは、AIが最も苦手にすることでしょう。
体験という五感を通して知覚することを、まとめあげて瞬時に言語化することが人間にはできますが、考えればメカニズムとしてはとても膨大な情報量を繊細に処理していることになります。
また、AIには体験していることのどの部分をメモすればよいかもそもそも判断ができないのです。
メモというのは特に重要なポイントだけをするからできるのであって、何から何までメモしてしまったら逆に何が重要なのかメモを読み返すとき一苦労です。
AIには「常識」がないので、この取捨選択の判別ができないのです。
② 常識を体感的に「記憶」しておく勉強
メモは重要だと思った「体験」をただ時の流れるのにまかせて、忘れてしまうのを防ぎます。
覚えておこうという意志を強く持っても、それだけでは長く記憶しておけないのが人間です。
「記憶に頼るな、記録しろ」という言い方で、メモを取ることを昔、わたしも先生に教わった覚えがあります。
書いたものを見返せば、ずっと忘れていた幼いころの記憶でさえ、掘り起こすようによみがえらせることも可能ですね。
③ 意味を理解するために「常識」を身につける勉強
体験をメモし、言語化しておくと、後で他の知識と結びつけることが容易です。
新しい事例に出会ったとき、今ある知識に結び付け、応用して判断できることが「常識がある」ということでしょう。
④ 文章の「意味」を理解するような勉強
言葉の裏や行間にある意味を読み取ることを、常日ごろ会話や文章を読む中で、わたしたちは行っています。
わたしたちは実感的な体験を積み重ね、体験のサンプルを集めることで、「空気を読む」直感的な判断力をみがいているわけです。
「意味」とは一面的ではないために総合的な判断材料として「体験」が重要になってくるのです。
2. できる子はみんなメモを取る

「メモを取る」という話でわたしが思い出すのは、大学時代、教職課程の授業を受けていたときのことです。
担当の大学教授がこんなことを言ったのをよく覚えています。
「これまで見てきた数多くの生徒の中で、できる子たちには1つ共通点があった。
何かと言えば、それはみんなメモを取る子たちだった」
「先生は授業中の説明をすべて板書するわけではない。
大事なことを板書しないこともよくあるもの。
そんなとき、できる子はその時、メモをしている。
しかし、そうでない子は聞き流してしまう、これが結局差になっているだろう」
その後わたし自身も指導する立場となって、このことを強く実感しました。
できる子は、板書以外の説明を聞きくと、テキストの端やノートにメモをしています。
次の授業のとき、その生徒のテキストやノートを見ると、前回書いたメモをさらに自分なりに色分けするなど、カスタマイズして自分のものにしているのです。
言われたことを、言われたとおりにやるのは、プログラミングです。それはAIができることです。
一方、何が重要なのかを判断し、それを自分なりの方法で身につけたり、アウトプットしたりはAIにはできません。
一見素朴な行動のように思える「メモ」は、判断をともなう実践なのがお分かりでしょうか。
勉強と意識せず、すべての体験を勉強に変えている1つの手段が「メモを取ること」なのです。
日記を書いたり、読書をしたり、感想を書くことも、自分の体験を言語化する活動です。
これらもメモ書きの延長です。習慣にできると理想的です。
メモを書くにも言葉を知らなければなりません。前提として、言葉の暗記は欠かせないことは念を押してお伝えします。
3. 国語はプログラミングできるのか?

AIを通して国語の勉強法について考えてきましたが、たどり着くのは次のような観点です。
言葉をうまく活用しようという態度は、本当はおこがましいことかもしれません。
言葉は、今生きているわたしたちが生まれる前からあるいわば大先輩です。
長い年月を経て今のかたちになっているのです。
わたしたちは普段、言葉を情報を伝達する道具として活用しています。
一方で見てきたように言葉は「記憶」や「思考」「体験」「常識」「意味」といったいわば人間が人間らしくあるためのよりどころでした。
AIが言葉を数値に置きかえて統計処理するのは、言葉の一面的な活用でしかありません。
「言葉をつかう」ことは、即生かせるスキルのようなものではありません。
長期間かけてようやく形成されるものです。
言葉を使ってやろうという態度ではなく、言葉に浸るような経験を重ねることで、時間をかけて言葉はその人自身となってあらわれ出るようなものでしょう。
それこそ時間をかけることで熟成されて、うま味を増すようなものです。
先々のための準備や仕込みは、人間なかなかできないものです。
プログラミングをすれば、すぐさま活用できるようなことに目移りしがちです。
しかし、言葉は本来そういった成り立ちのものではないのです。
AI時代が迫ってくるから言語をプログラミングしようとか、明日試験があるからせっぱ詰まって暗記しようという安直なものでなく、手間ひまかけて、自分の言葉を蓄えていきたいものです。
 2023年度 出題作品予想!中学入試の国語はなぜ新書から出題されるのか?
2023年度 出題作品予想!中学入試の国語はなぜ新書から出題されるのか?10冊の新書を紹介 国語の問題として、出題される本の多くが新書です。 この事実を知っていれば、志望校の入試問題を事前に読ん…





